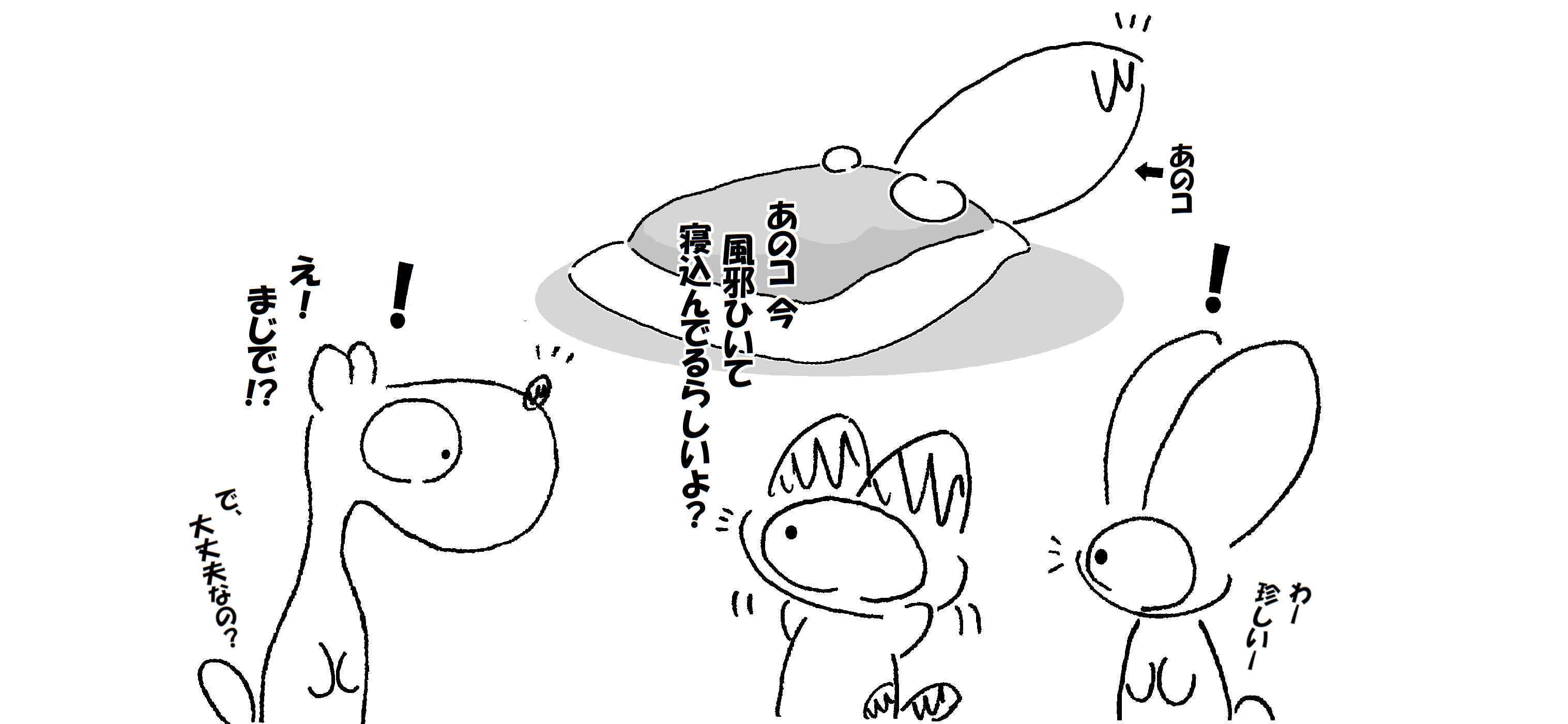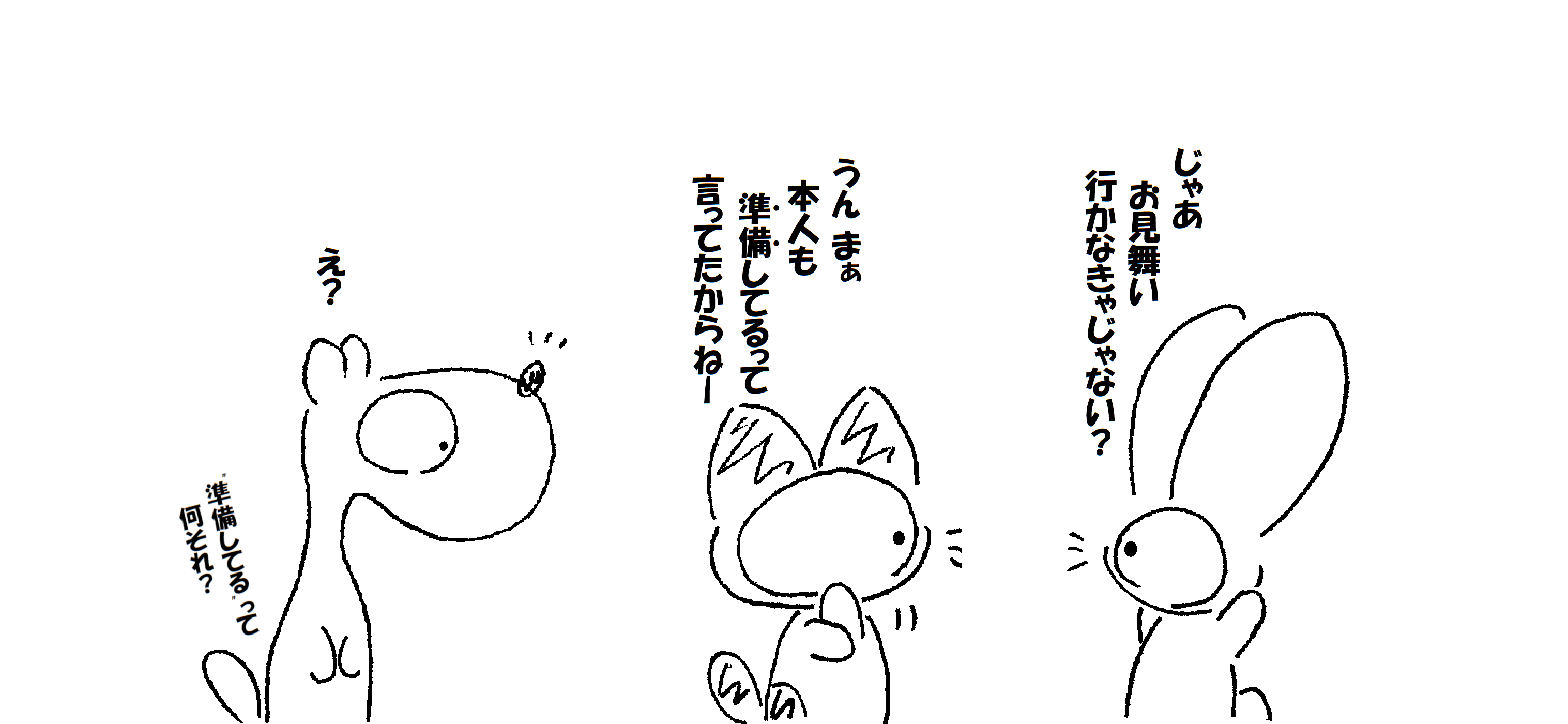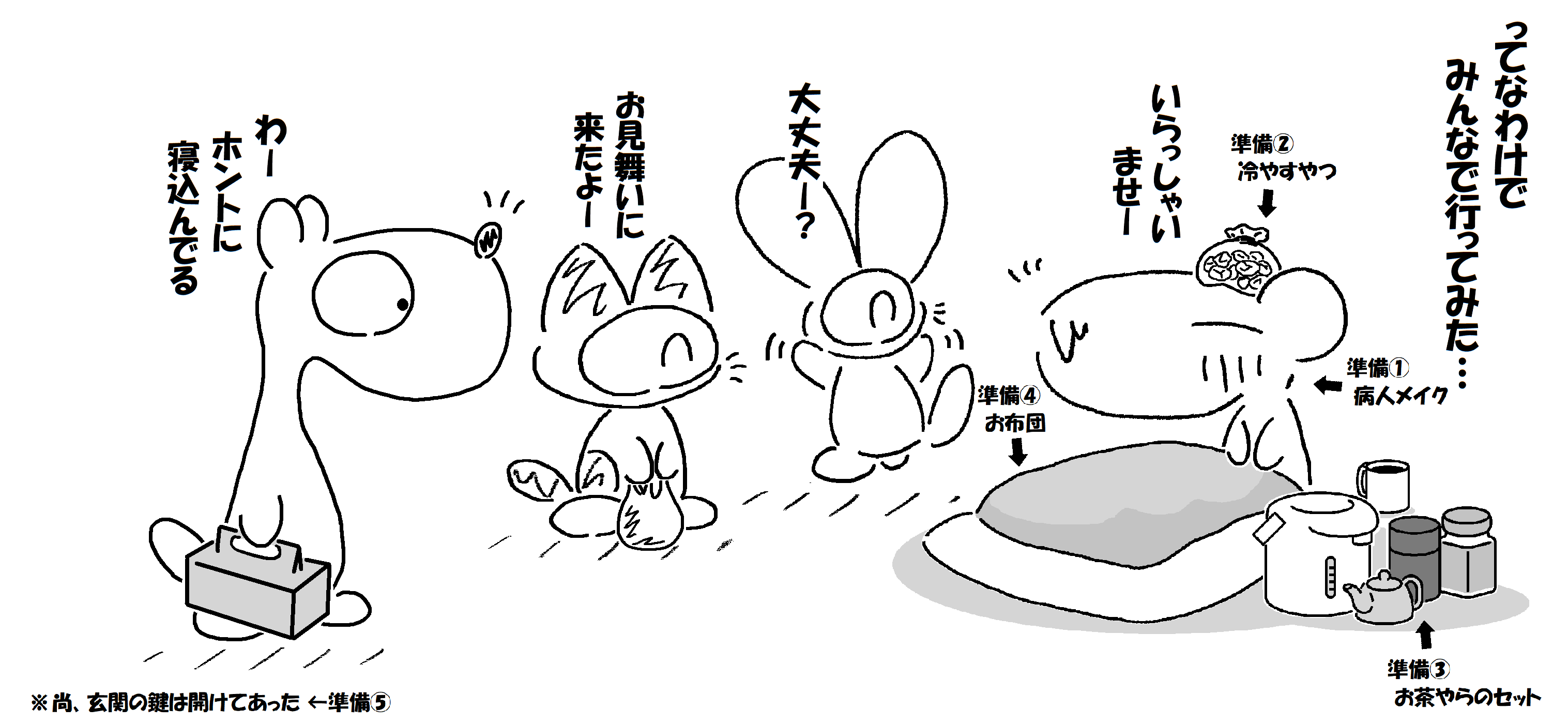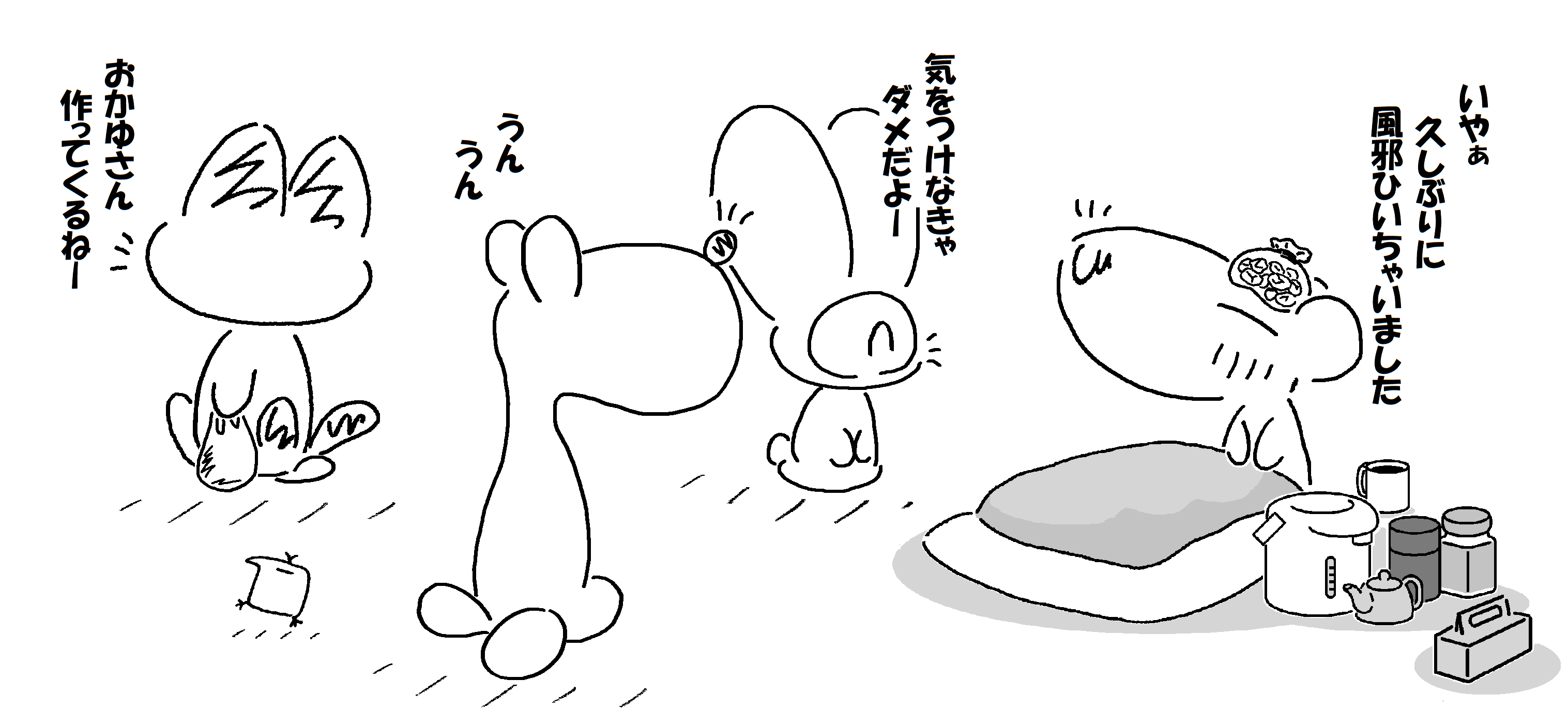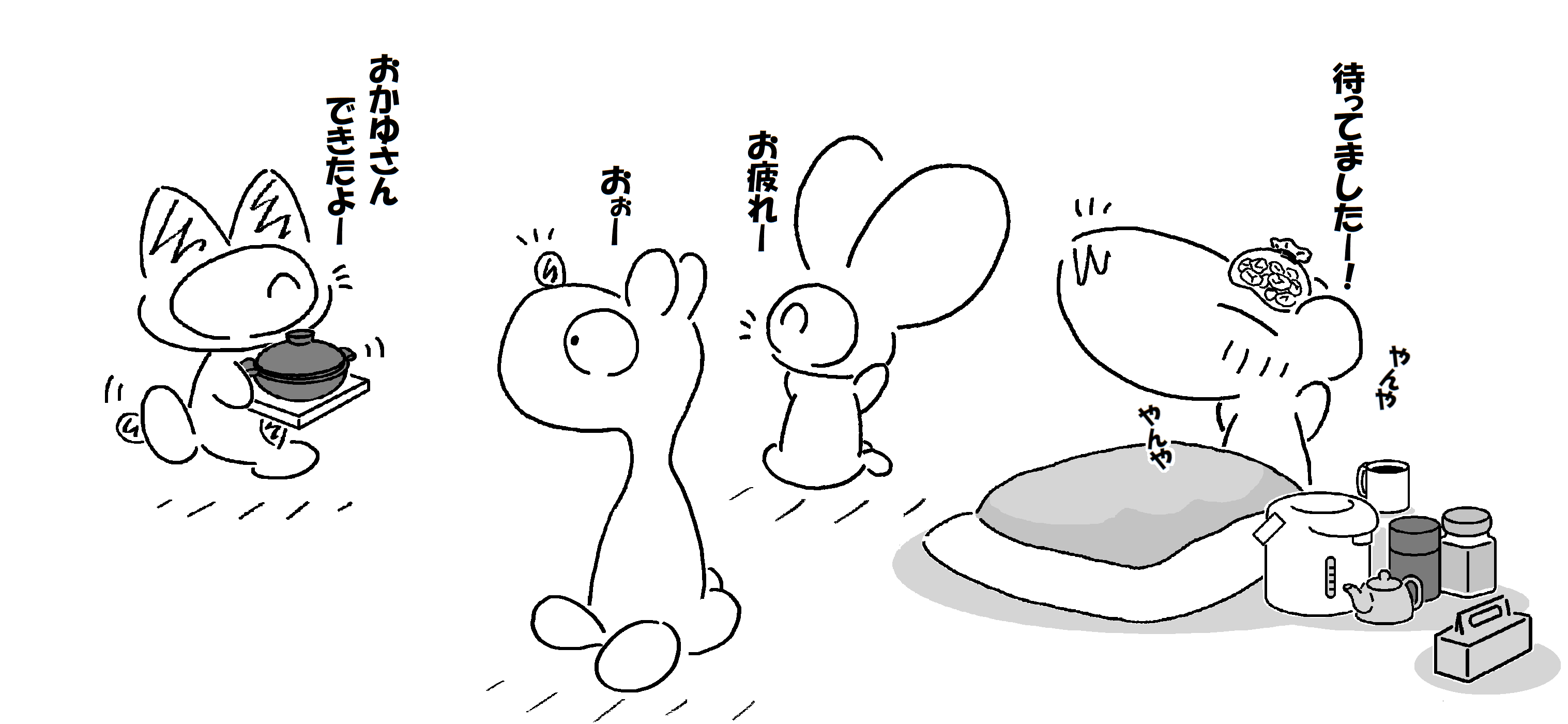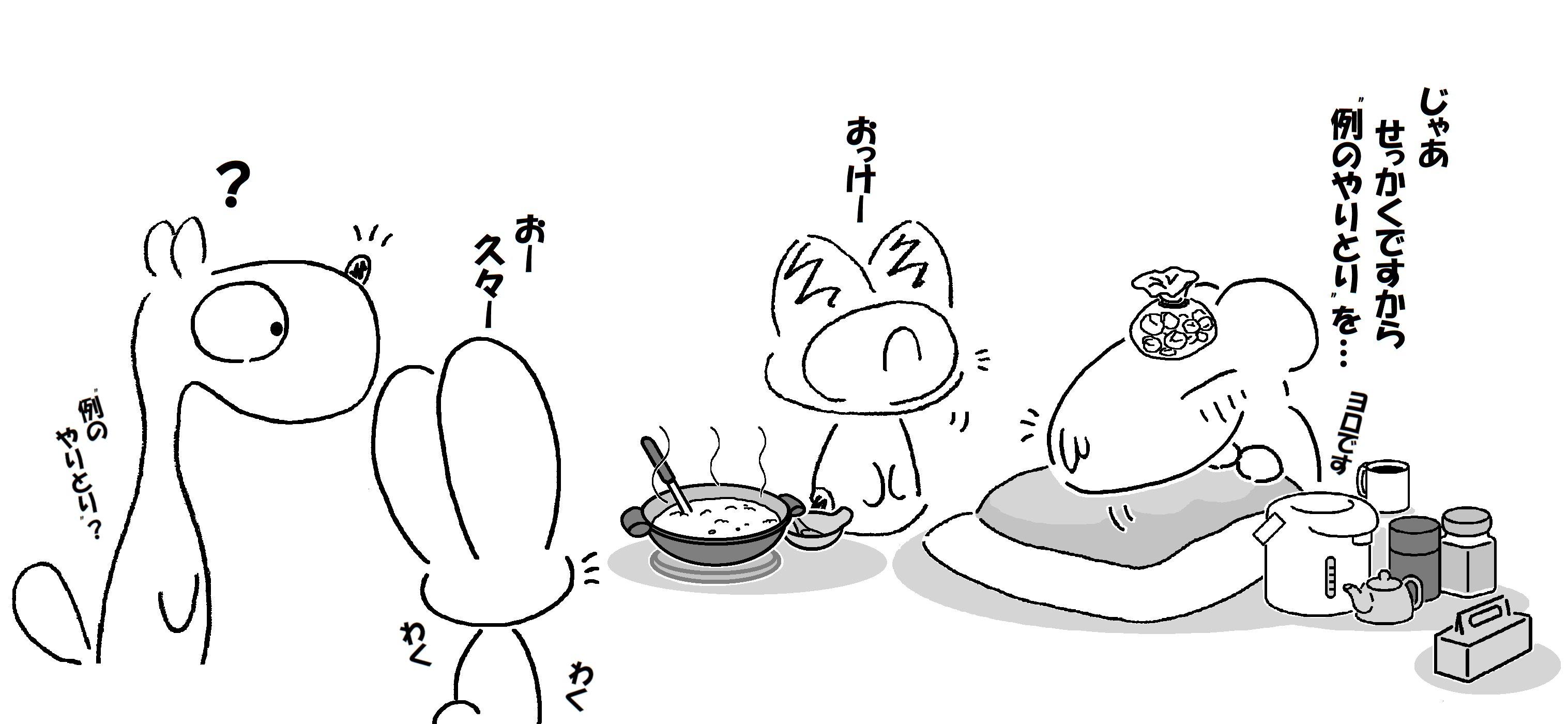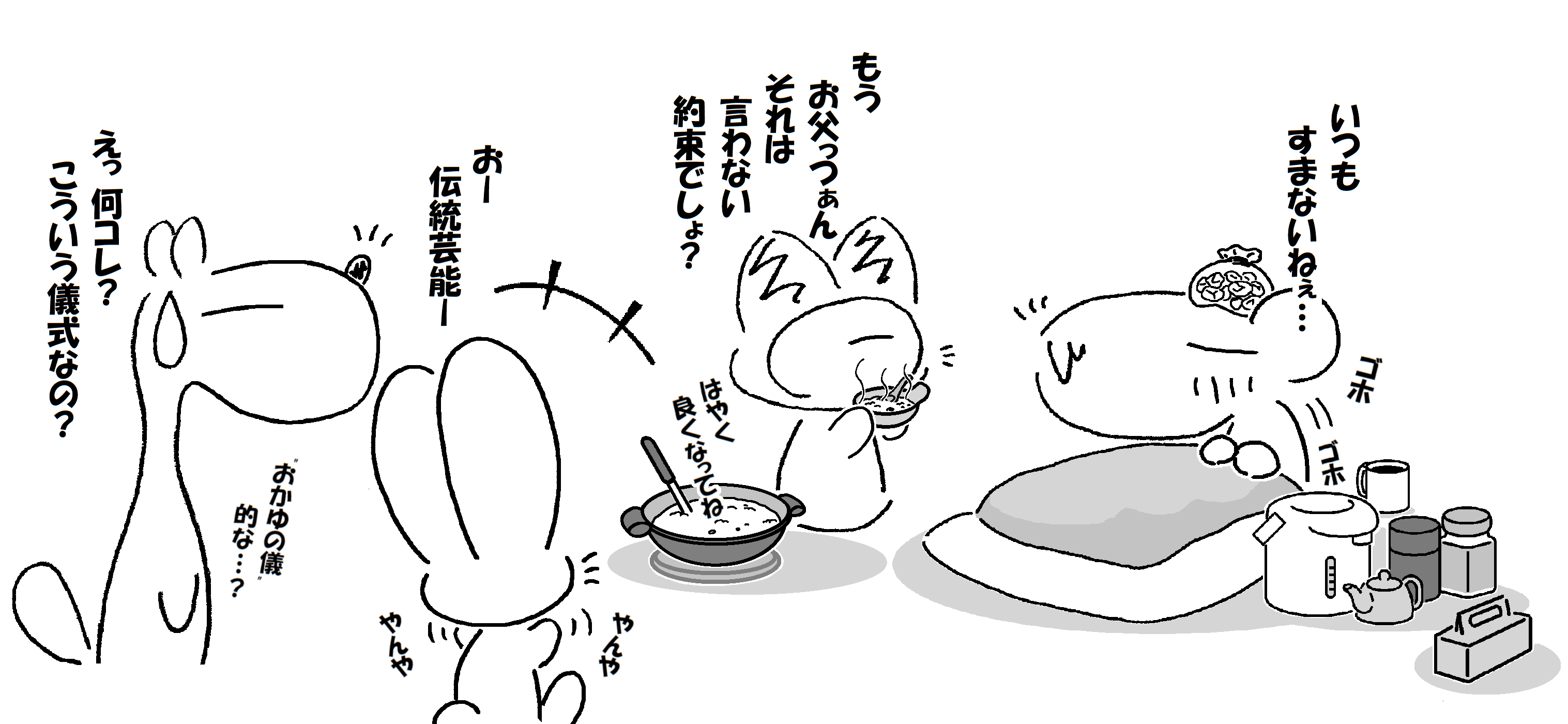米(うるち米)や麦、粟、ソバなどの穀物類や豆、芋類等を水分多めに煮詰めた料理です。世界各地で様々な穀物類が主食として食されていますが、同様の調理方法が用いられているものも多いですよね? 美味しそうなものもたくさん。「お米」が主食とされてきた日本も、勿論例外ではありません。稲作が始まった当初から、この”お粥”って料理は広く食べられてきたようです。一応、生米から煮る方法と一度炊き上げたご飯を煮る方法がありますが、どちらも”お粥”だそうです。特に後者は、固くなったご飯を再度美味しく食べる方法として用いられてきました。”鍋料理”等の〆に作る”雑炊”や”おじや”なんかも”お粥”の一種と考えて頂いていいでしょう。”雑炊”や”おじや”のように「お米」以外の具材が入っているものの場合、この調理方法の勝手が非常にいい点が、具材追加や追加の味付けが半無限に可能ってところです。よほど味や風味のクセが強い食材や調味料でない限り、大体美味しく食べられますから。カレー類と青魚の類は要注意ですかねぇ。あと、冷めちゃうと極端に味が落ちちゃうってことにもご注意ですかね・・? まぁ、”ごった煮”なんて呼び方もあるくらい、とっても自由度の高い料理です。また、日常食として親しまれてきたと同時に、病人用の料理、幼児の離乳食としても広く食されてきたりしました。「お米」を煮詰めていく過程で、お米がいくらか溶けだした上澄み液は”重湯(おもゆ)”っていいまして、古来から流動食の元祖みたいなものとして食べられてたんですよ?
さて、この”お粥”と言う料理。作る際の水とお米の分量比によって呼び名が違います。と言っても、それぞれの名前が全く違ったものに変わるわけではなく、”お粥”内におけるお米の含有率みたいなのが明示された名称になるだけなのですが。でも、その割合がちゃんと定義づけ(農林水産省で公式に説明されております)されてるんですね?
こんな感じです。
・全粥(米:水=1:5、重湯なし)
・七分粥(米:水=1:7、全粥:重湯=7:3)
・五分粥(米:水=1:10、全粥:重湯=1:1)
・三分粥(米:水=1:20、全粥:重湯=3:7)
そんな”お粥”ですが、食されてきた歴史が長いこともあって、日本では特定の月日に行事食として食べる文化が出来上がっています。よく知られているのは、”七草粥”と”小豆粥(さくら粥)”。後は”茶粥”ですかねぇ。せっかくですから、少しご紹介しておきますね~♪

・七草粥
一年の無病息災を願って、一月七日に食べられるお粥です。冬のこの時期、収穫できる野菜の類は非常に少なかったわけです。そんなこの時期でも収穫できる”春の七草”と呼ばれる野菜(どちらかと言うと、食べられる”野草”って言い方が正しいんですが)を入れたお粥を食べるんですね。セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ。お正月明けのスーパー等には、これらをセットにしたパックなんかが並べられてます。昔は、その辺の野っ原や山なんかで見つけることができたもんなんですよ? とってもあっさりした、それでいてとってもしっかりとした”野原”のような味がするお粥です。まぁ、具材があくまで”野草”ですから・・
・小豆粥(さくら粥)
こちらは小正月(一月十五日)に食べられる小豆入りのお粥です。その小豆によって薄桜色にそまった見た目から”さくら粥”って呼ばれたりもします。お正月に神前にお供えした”鏡餅”を”鏡開き”(神前から下げて分ける行事です)した際のお餅を入れたりする場合も。こちらも基本的には、無病息災を祈願したものです。
・茶粥
伝統的な郷土食として主に西日本のいくつかの地域で見られる代表的な粥料理の一つ。元は、1000年以上前から奈良周辺のお寺で僧侶達によって食されていたと言われており、やがて一般世間にも広まったとか。ほうじ茶や緑茶で作るお粥です。おそらく、他の種類の茶葉を使って作っても、それなりに美味しいはずです。
冬時期は、各家庭においても普段から”お鍋”なんかをすることが多くなります。と言うことは、その〆に”雑炊”をしたり、残り汁で”おじや”を作ったりすることも増えるわけです。調理が楽ですし、何よりも温かいですから。そのせいもあってか、この時期は”お粥”の類をしょっちゅう食べてるような気になるんです。実際、”私”はしょっちゅう食べてたりします、はい。この冬は、みなさんも是非是非お試しあれ。




_op.png)