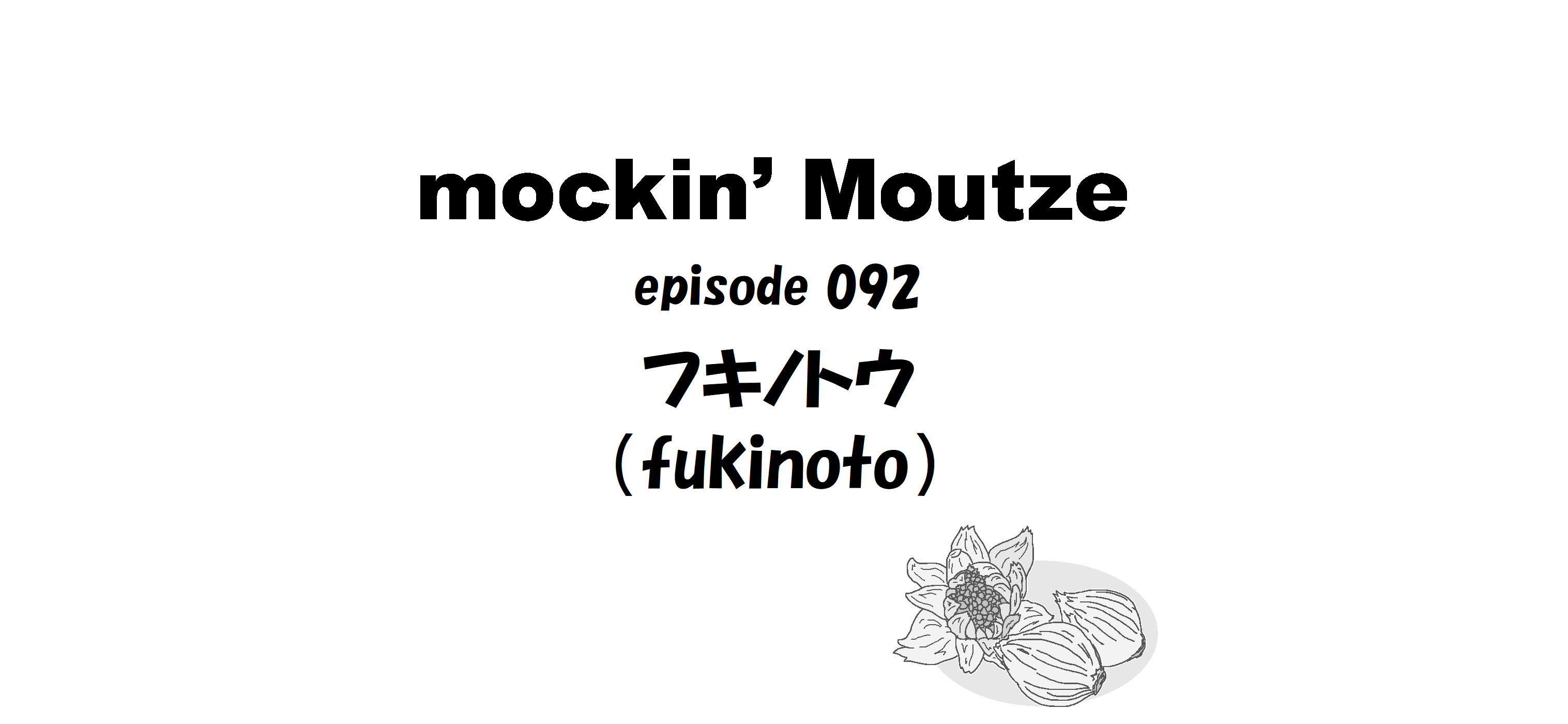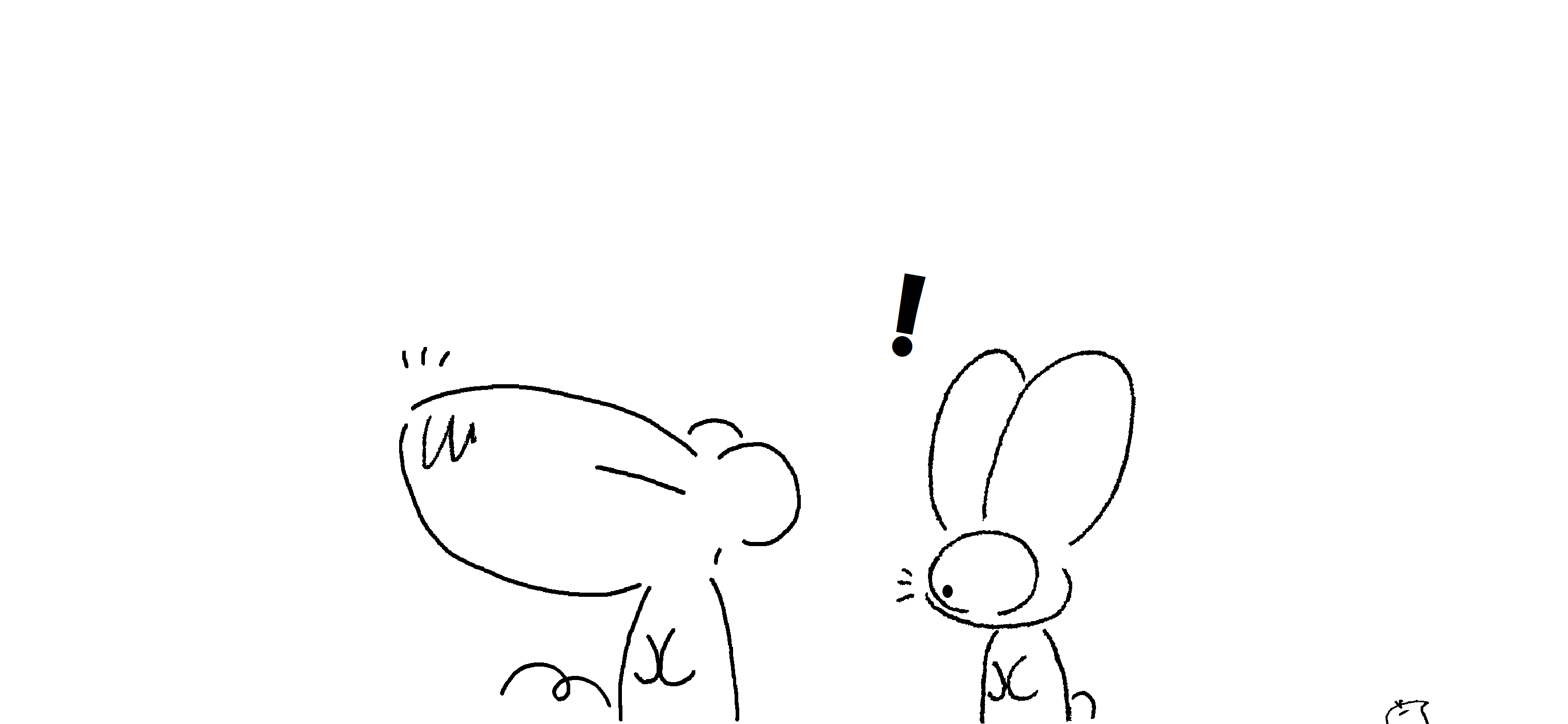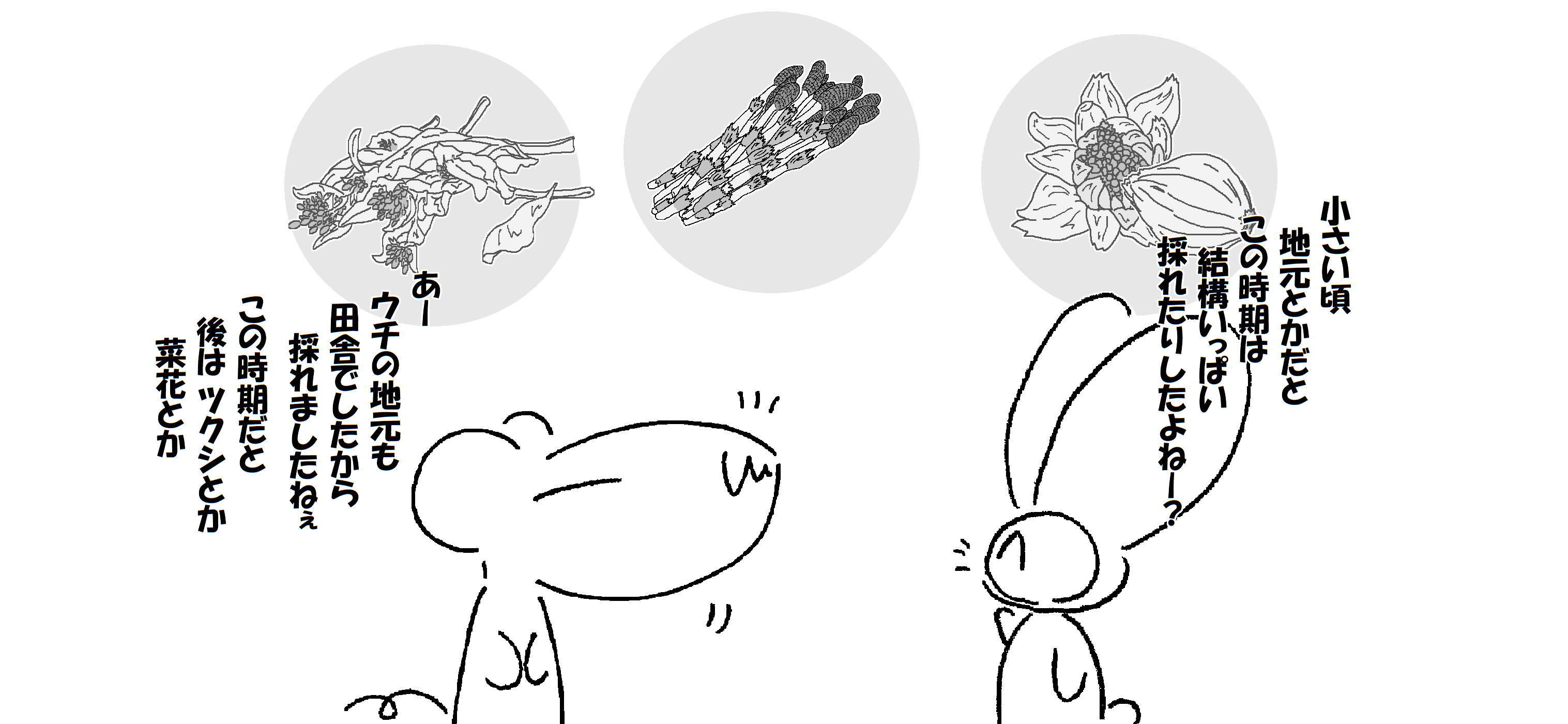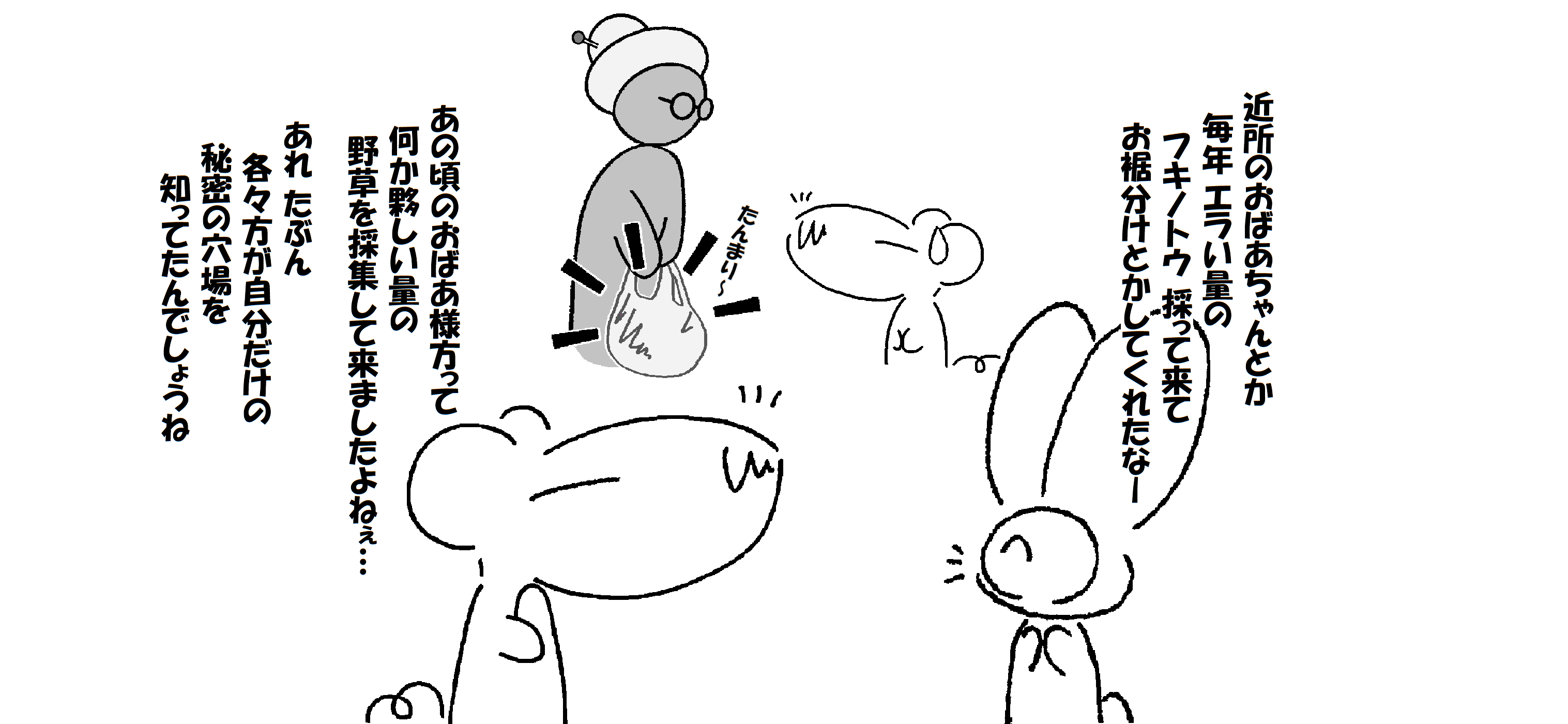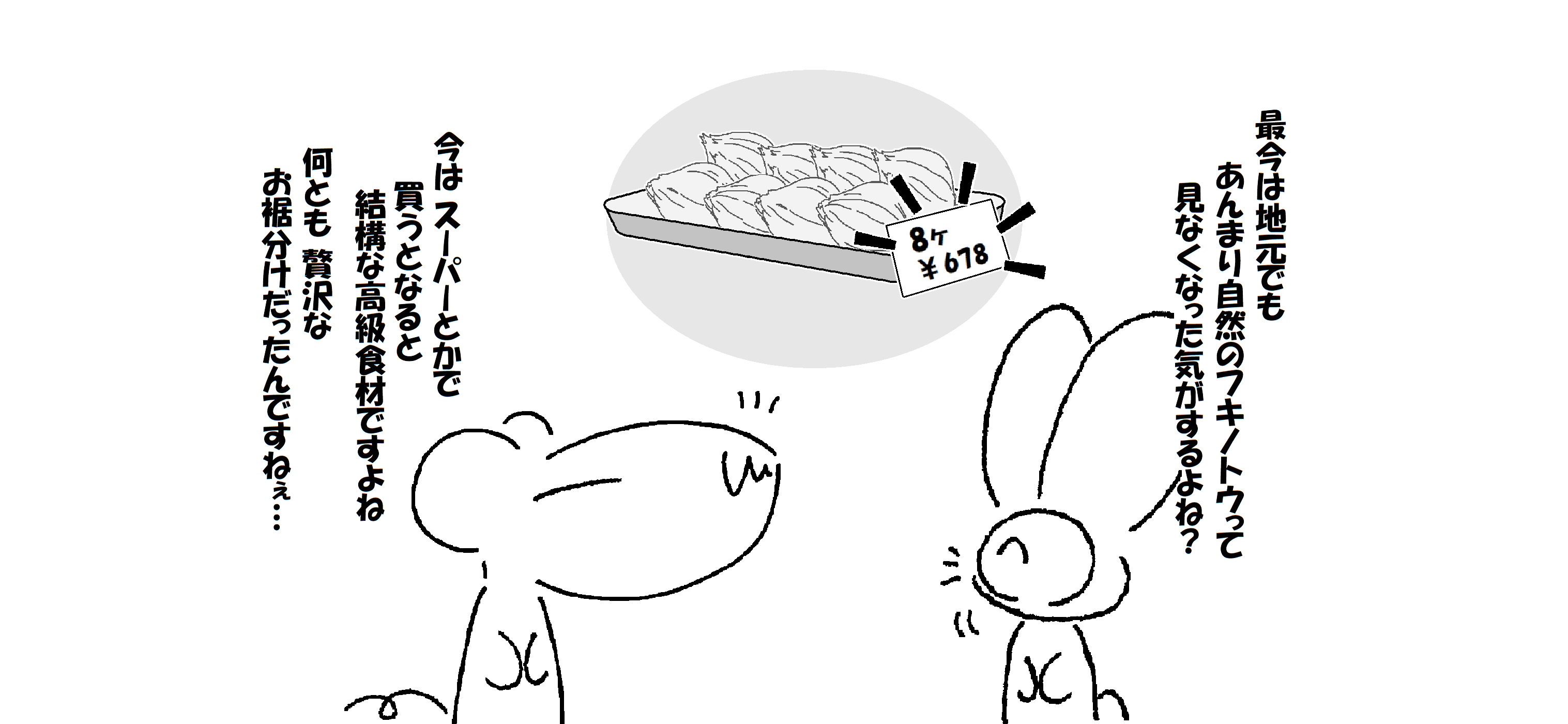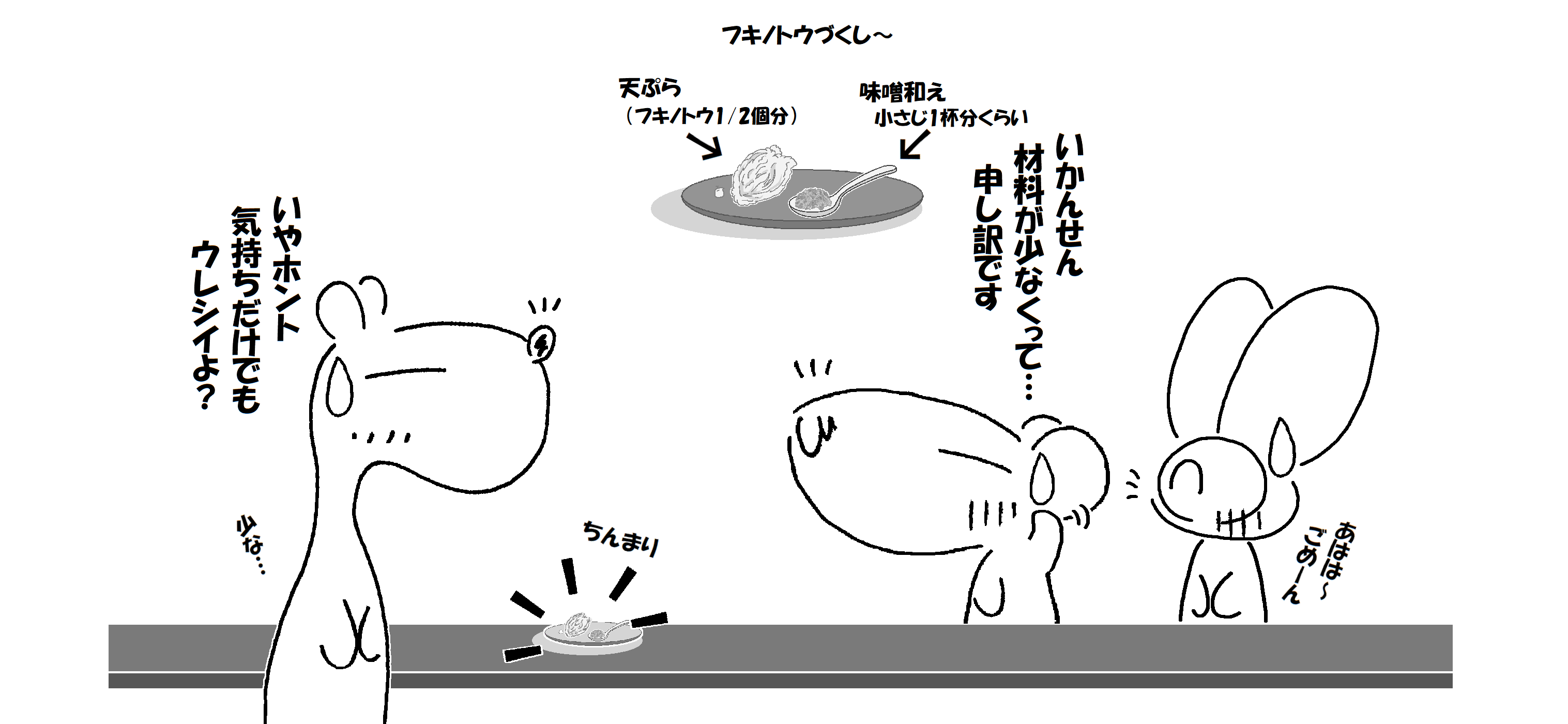ご存知の通り、日本では非常に多くの野菜が料理に用いられ、食されています。特に和食料理、とりわけ伝統的な和食料理の材料は、その多くが野菜だったりします。近代以前までの日本の食文化は、菜食寄りだったんです。仏教における肉食を禁じる教えの影響が強かった上流階級では勿論のこと。一般の人々の食生活においても、居住地域差はいくらかあったものの、基本的にはその傾向が強かったようです。よって、和食料理に用いられる食材は、自然と野菜中心になっていったわけですね? さてさて、そんな日本の食文化において欠かすことができない野菜ですが。実のところ、日本原産の野菜とされているものは非常に少ないんです。このことは、現在一般に食されている野菜についてばかりではありません。伝統的な和食料理として知られている料理に用いられる野菜も実はその大半は海外が原産なんです。その多くは、大陸から稲作が伝わった時代以降に、交易を通して持ち込まれたものが国内でも徐々に栽培されるようになったと言われています。そして、長い年月のうちに品種改良が重ねられて現在に至るわけです。”京野菜”、”加賀野菜”と言った、地方の伝統的なブランド野菜なんかも元々は日本原産ではなかったりするんです。そんなわけで以下では、数少ない日本原産の野菜のうち、一般に流通している代表的なものをいくつかご紹介しておきましょう。日本で和食料理をお試しになる際には、ご参考にして頂ければです。(*”▽”)∩
三つ葉(ミツバ)

セリ科の多年草で、その名の通り3つに分かれた葉が特徴。日本のハーブと言われるように特有の香りを持ちます。おひたしや和え物の他、お吸い物や丼ものの具材としてよく用いられます。かつ丼や親子丼に乗せられている緑の葉っぱみたいなやつ、アレです。
芹(セリ)

セリ科の多年草で、春の七草の一つとしてよく知られています。おひたしや和え物で食されることが多い他、鍋料理の具材としてもよく用いられてきました。爽やかな苦味と心地良い歯触りが特徴です。
蕗(フキ)

キク科の多年草。ツボミは特に”フキノトウ”と呼ばれ、春の旬の野菜として知られています。フキノトウは主に天ぷらや和え物にして食されます。葉や茎の部分はアク抜きをして煮物や炒め物に調理されることが多いですね。
茗荷(ミョウガ)

ショウガ科に属する多年草です。蕎麦やうどんの薬味としてよく知られています。天ぷらや和え物なんかに調理しても美味しいですね。独特の甘苦い風味が非常に特徴的で、その香りは記憶をなくさせてしまう効果がある、なんて逸話があるほどです。
山葵(ワサビ)

アブラナ科に属する多年草で、日本を代表する薬味の一つとして海外の方達にもよく知られています。地下茎をすりおろしたものが鮨や刺身の他、蕎麦やうどん等によく用いられます。ちなみに葉や茎の部分も食することができます。わさび菜と呼ばれ、おひたしや炒め物なんかに調理されます。こちらはすっきりとした苦味と香りが特徴です。
独活(ウド)

日本の代表的な山菜の一つです。ウコギ科タラノキ属の多年草植物。やわらかい若芽が食されます。天ぷらや和え物にすると非常に美味です。
山芋(ヤマイモ)

ヤマノイモ科ヤマノイモ属の多年草です。”自然薯(ジネンジョ)”とも呼ばれますね。すりおろして食される(”とろろ”って料理です)ことが多いですね。天ぷらや汁物の具材としても用いられる他、千切りにしたものを和え物に調理されたりします。和菓子の素材としても用いられます。非常に強い粘りが特徴。
椎茸(シイタケ)

日本で食用にされるキノコ類の代表とも言えるキノコです。シイタケの他にも、エノキダケ等の国内に自生していたキノコ類はかなり昔から食されていたんだそうです。20世紀以降は人工栽培の方法が確立したことにより、そちらが一般に流通するようになりましたが、それ以前は野生のものが採取されていました。尚、現在一般に食されているものは、元々は大陸産のものを人工栽培したものが大半です。シイタケは何と言っても出汁をとるための食材として、和食料理には欠かすことができません。その出汁は、炊き込みご飯や麺類、汁物等々、あらゆる料理に利用されてきました。また煮物や鍋料理等の具材としてよく用いられます。