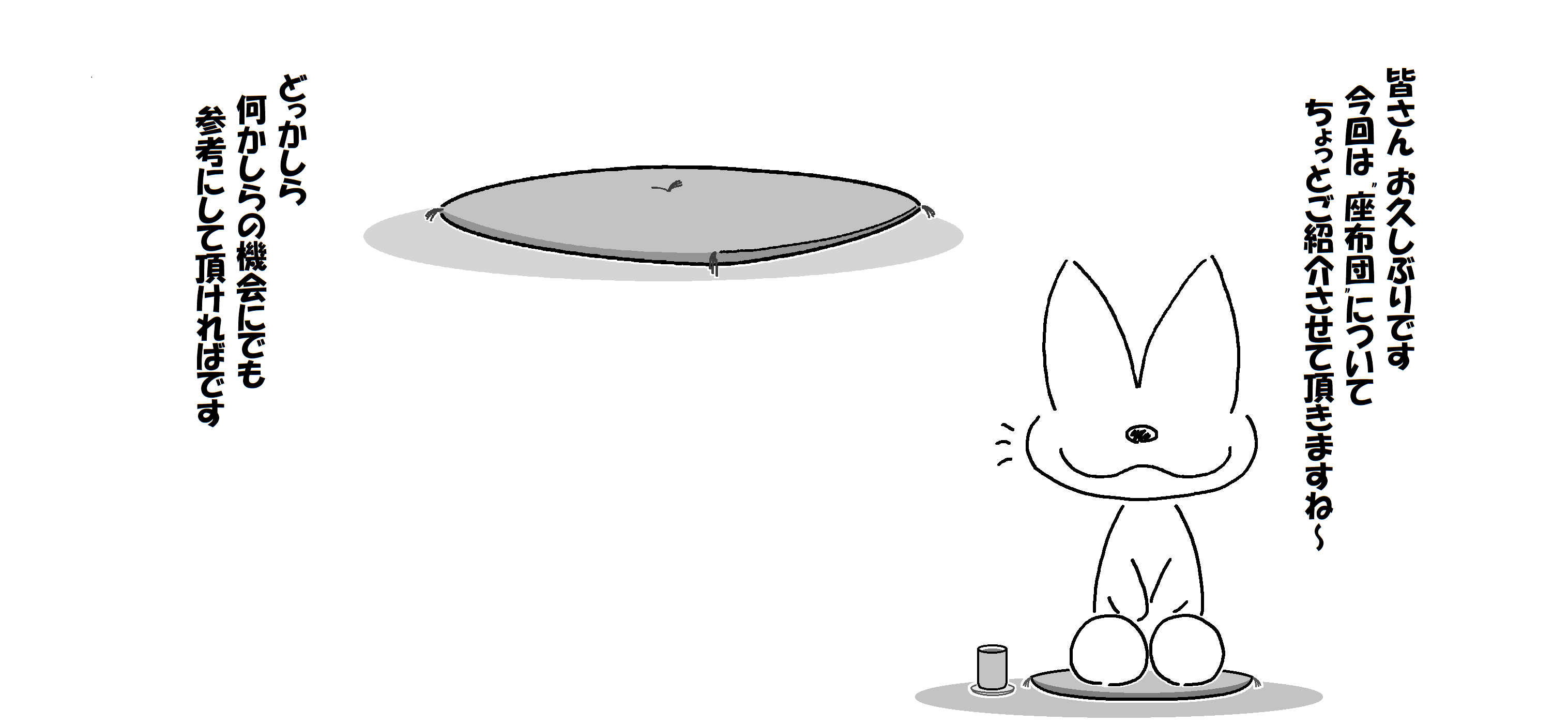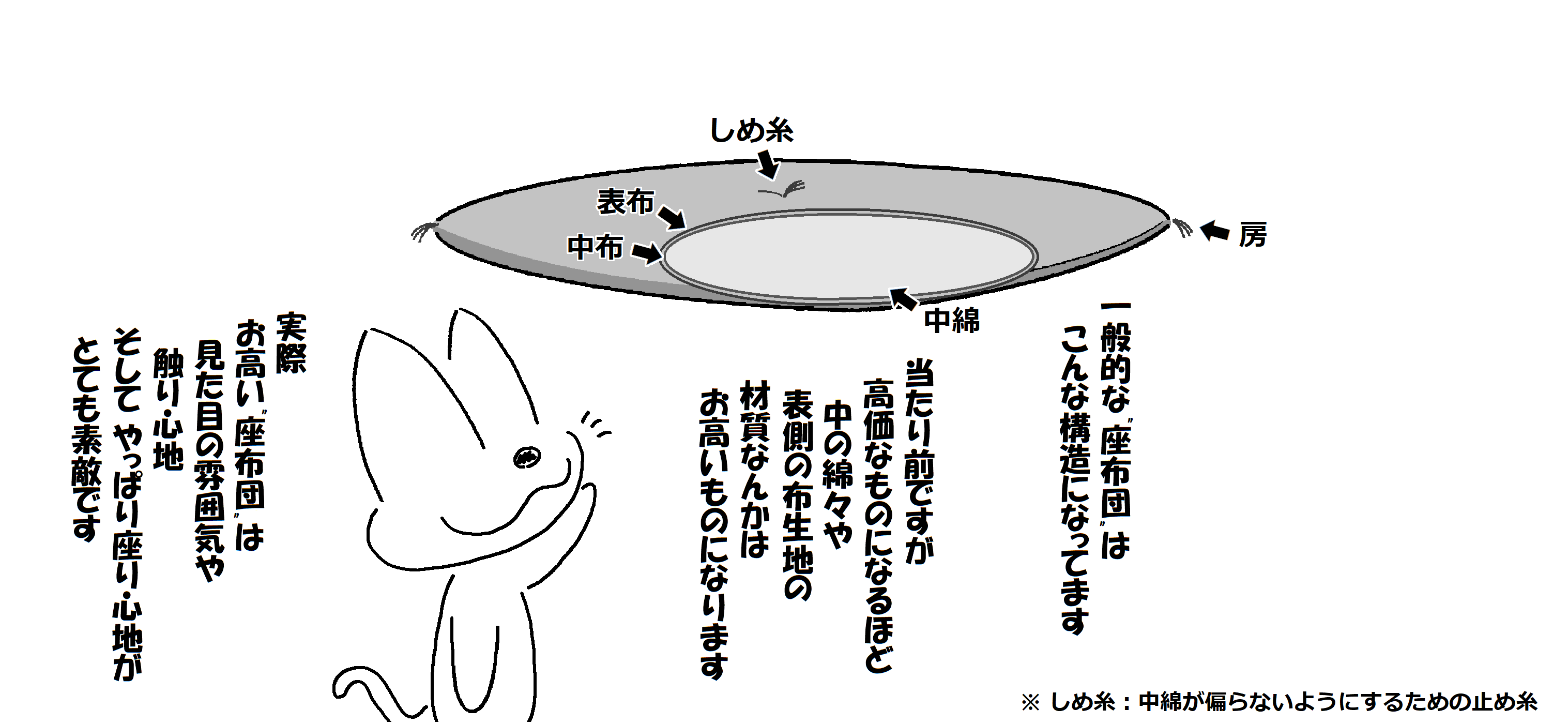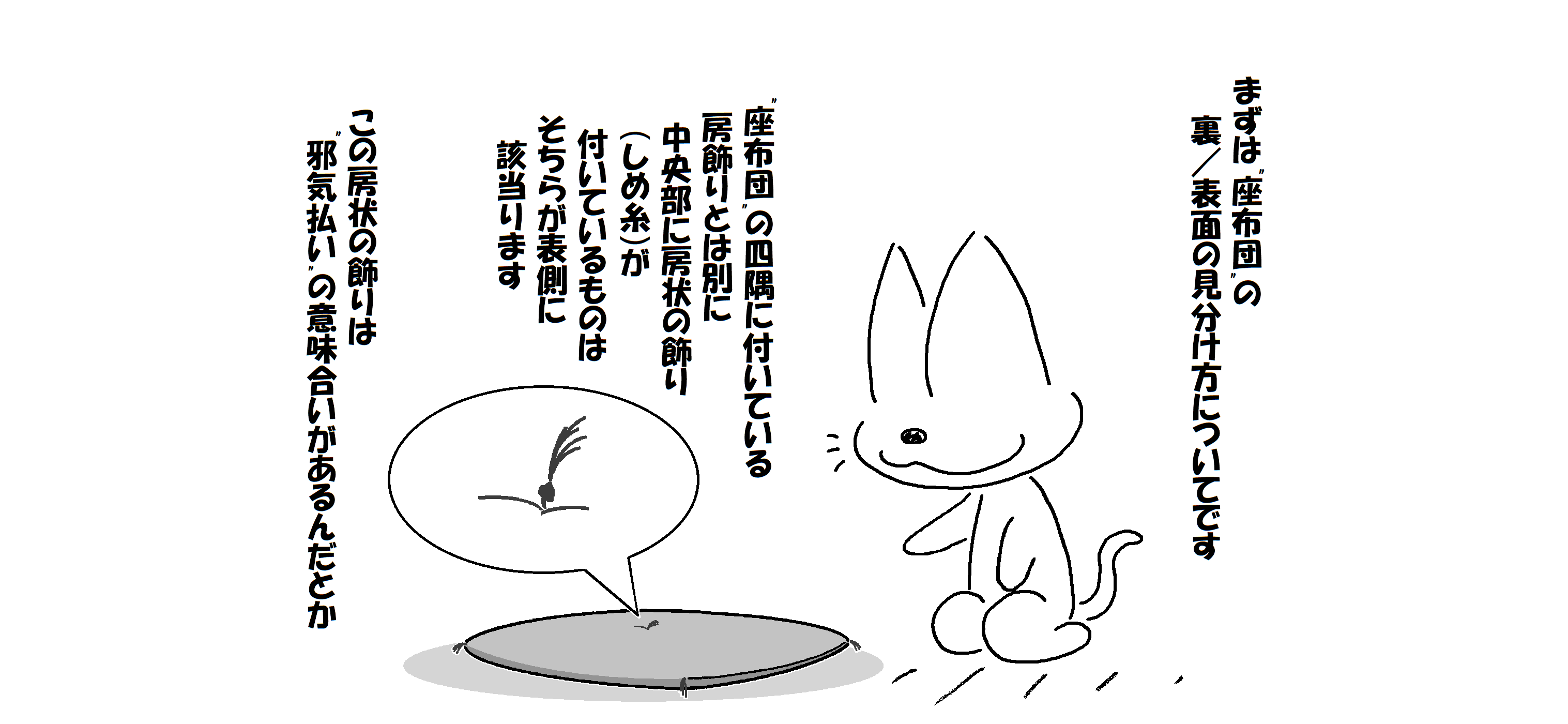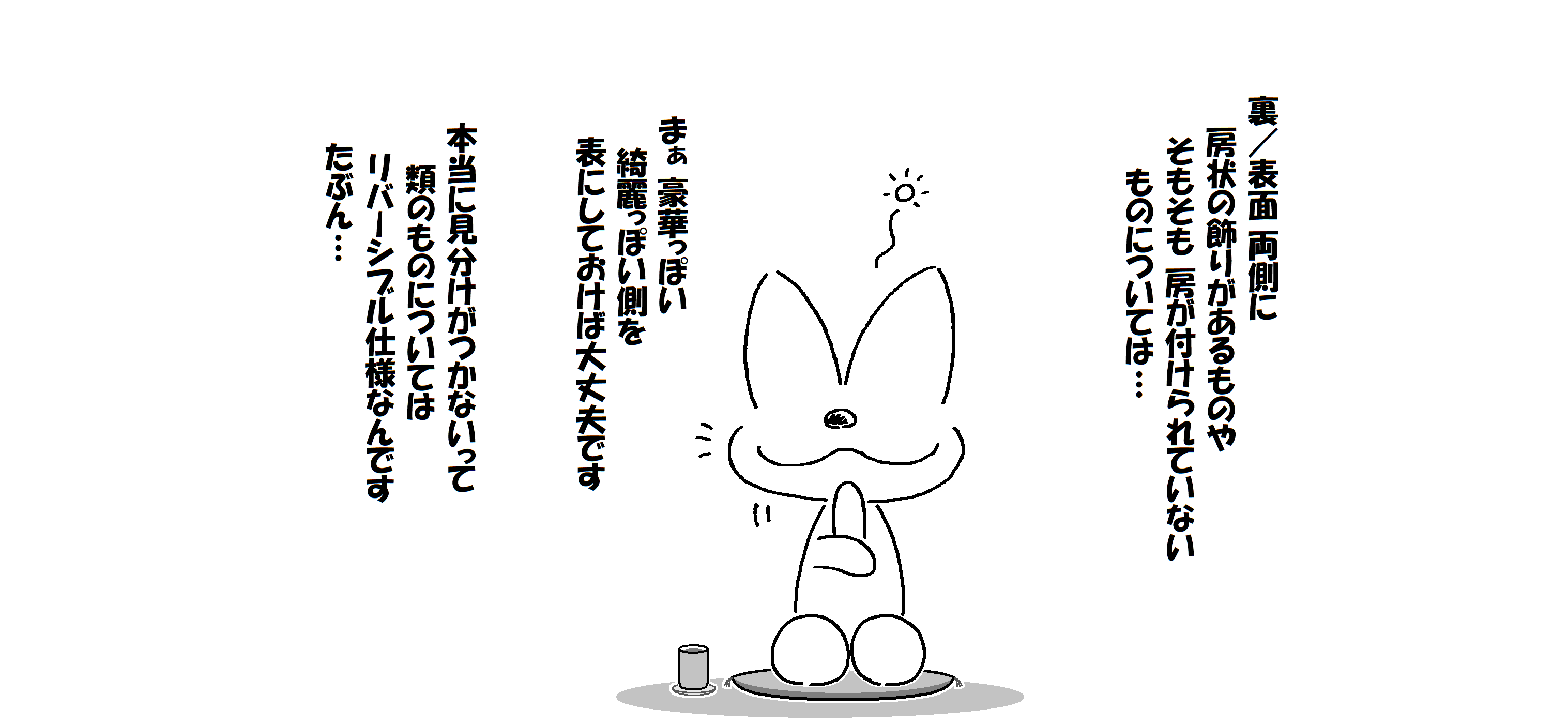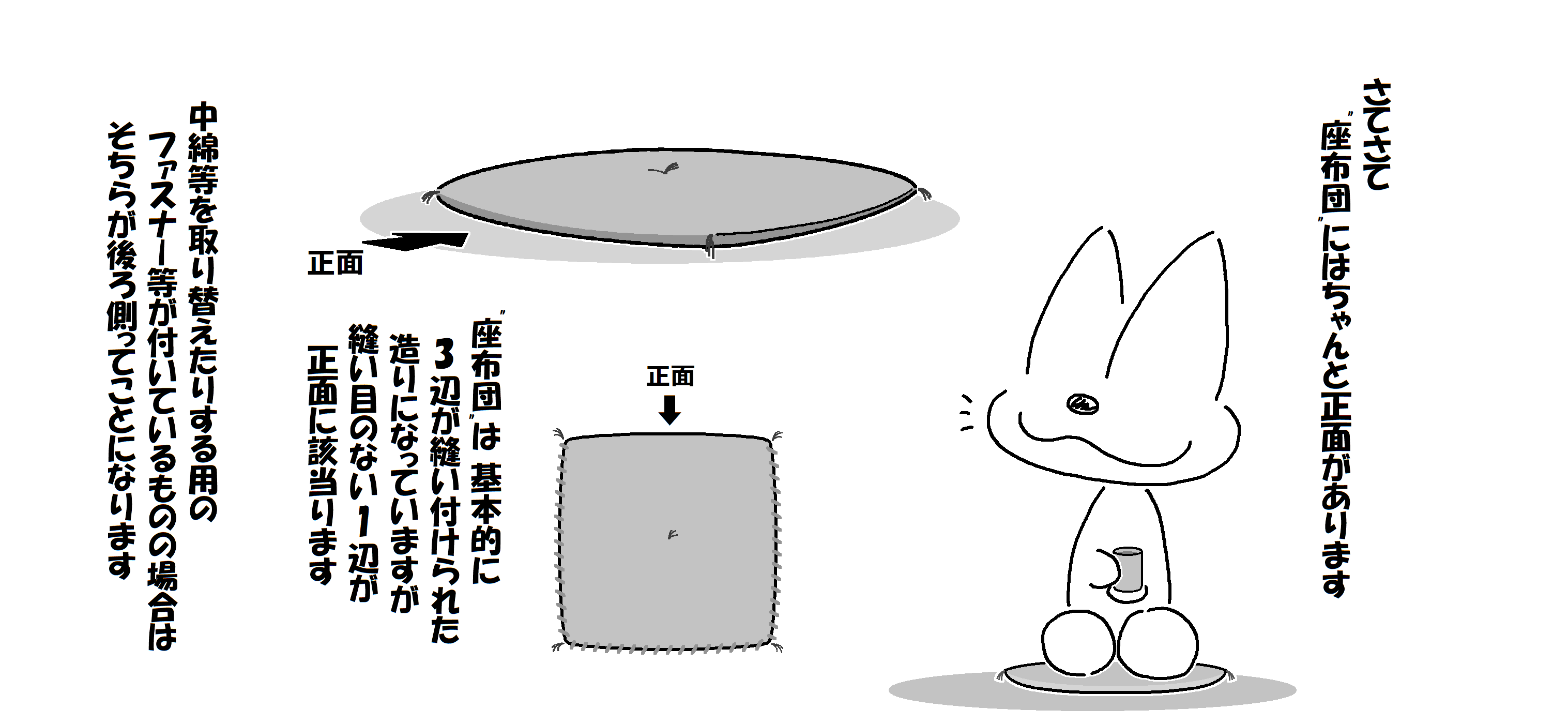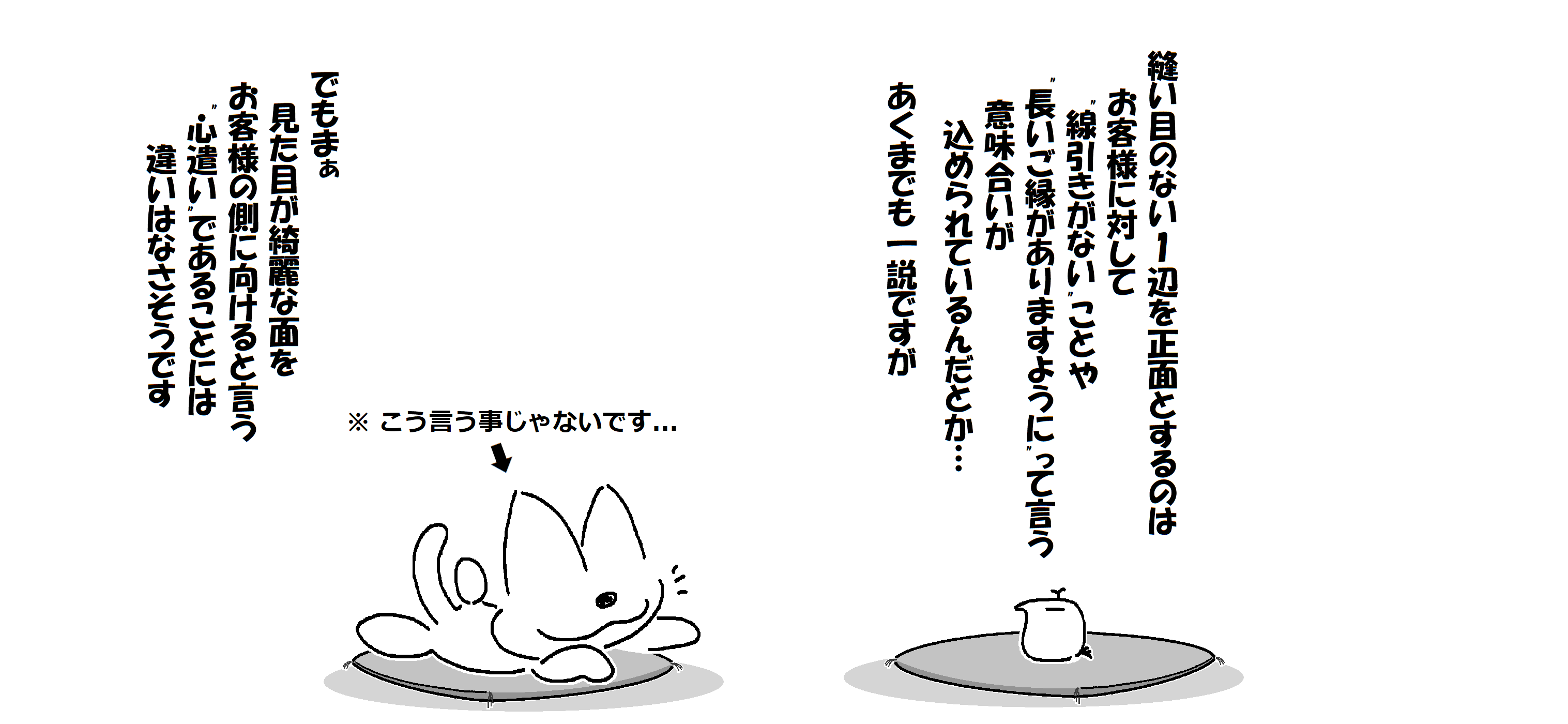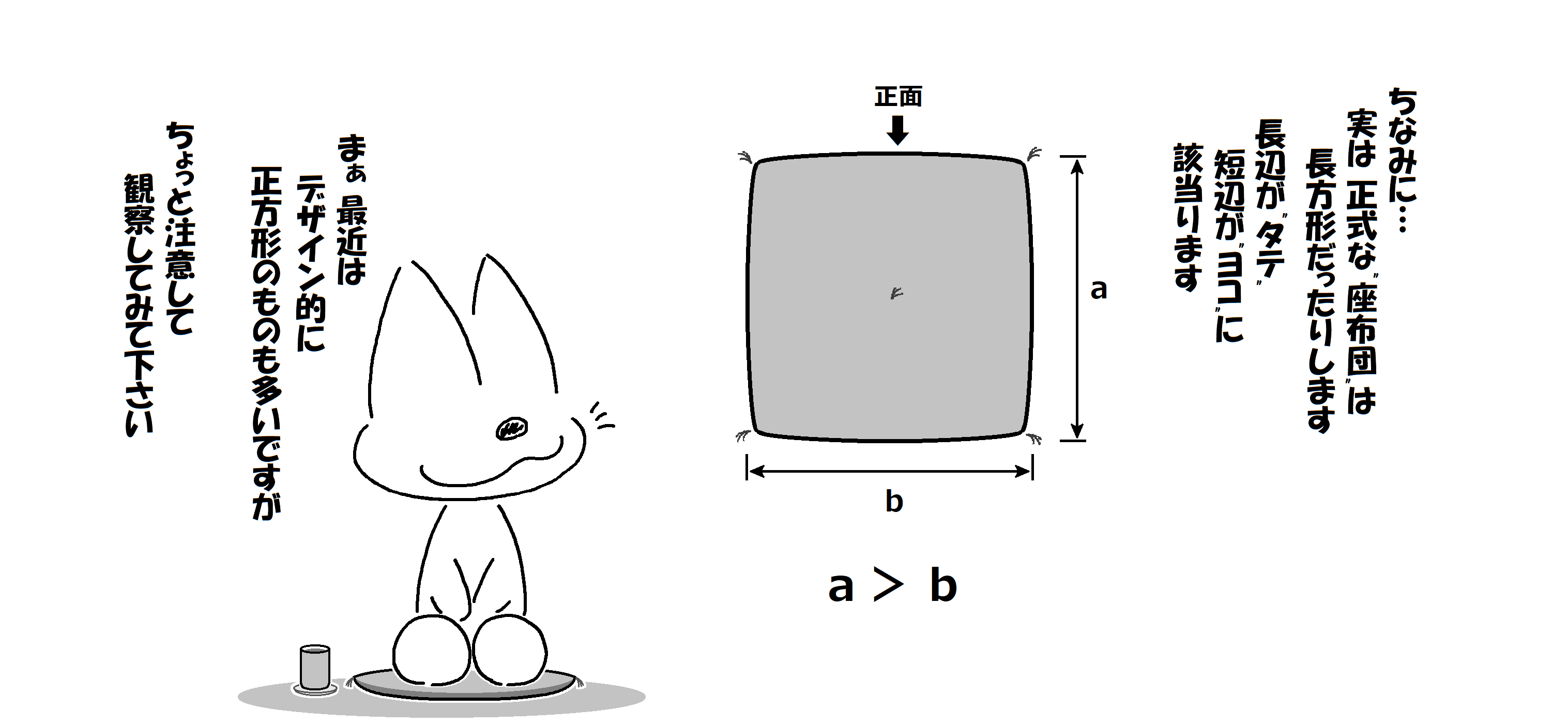床生活ならではの生活用品ですね。決してご自宅にいらっしゃる猫様が鎮座するためのものではありません。腰を下ろすためのものなので、所謂クッションとはやはり異なるものです。実は文化的にはなかなか奥深いものだったりするんですね。
元々、木の床に直に座るのはちょっとアレだなってことで畳が敷かれるようになったんですが。やがて、あれ?畳に直に座るのは何かアレだなってことで茵(しとね)というものが更に敷かれるようになりました。この茵(しとね)が「座布団」の元祖にあたるのだとか。茵(しとね)は、小さい正方形状の薄手の畳で周りを飾り布等で装飾したものです。百人一首の絵札なんかでちょろっと見えてたりするやつです。そんな茵(しとね)にも満足できず、もうちょっと厚みとか柔らかさがないとやっぱりアレだなってなったらしく、更に色々とあった末に布の中に綿をぎゅぎゅっと詰めた今の「座布団」の形になったそうです。江戸時代中期、今から三百年ほど前ですね。
「ちょっとアレ」「何かアレ」「やっぱりアレ」・・つまりは権力者とか目上の人間に対する敬いってやつです。木の床に直座りから少しずつ地味に嵩増ししていったんですね。一気に嵩増ししなかったり、敬われる側もそれでも床生活から抜け出さない辺りは何とも日本らしい気がしますが・・「座布団」は相手への敬いとか心遣いが込められたアイテムだったりするんです。畳敷き/板間に限らず、和室では基本的に「座布団」が用意されています。当然、その使い方には作法があるわけです。お客様への勧め方、勧められた側の対応の仕方・・シチュエーションにもよりますが、実は結構細かかったりします。一つ一つ説明するのはさすがにちょっと何かやっぱりアレですので、ここでは最低限と言いますか、基本的な作法にのみ触れますね。
まず、勧められるまでは座ってはいけません。一通り挨拶を済ませてから家主(部屋の主)が勧めるんですね。座る際には「座布団」を踏んづけてはいけません。「座布団」の位置や向きを変えるのも基本はNG。家主側に失礼にあたります。膝で這い寄るように座布団に上がり、基本的には正座します。家主側が「楽にしてください」とか「足崩して下さいね」と言ってから、胡坐なり横座りなりに変えて大丈夫です。離席する際は一言断ってから。やはり「座布団」を踏んづけてはいけません。
大体これらのことが基本的な作法です。必ずしも求められるものではありませんが、折角ですので今回を機に知っておいて頂ければ。
本当に余談ですが・・古今東西問わず、猫様は「座布団」をとても気に入ります。しかも初見にもかかわらず実にあっさりと馴染んでしまいます。やっぱり、生来からの「敬われる」気質があるんでしょうかね?




_op.png)